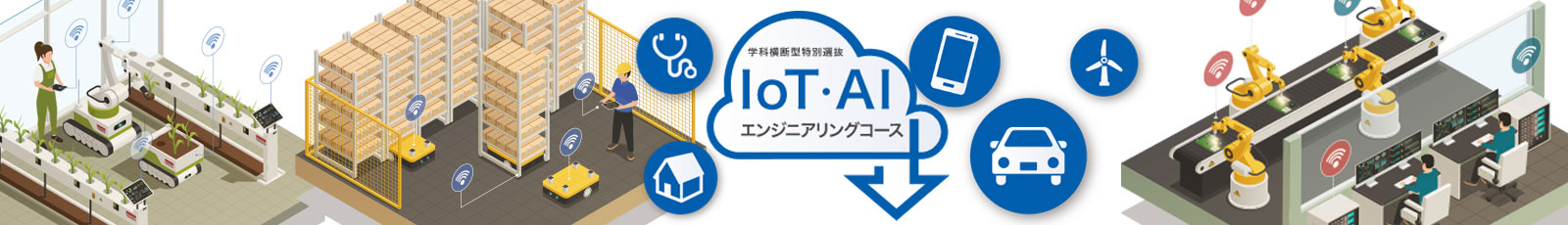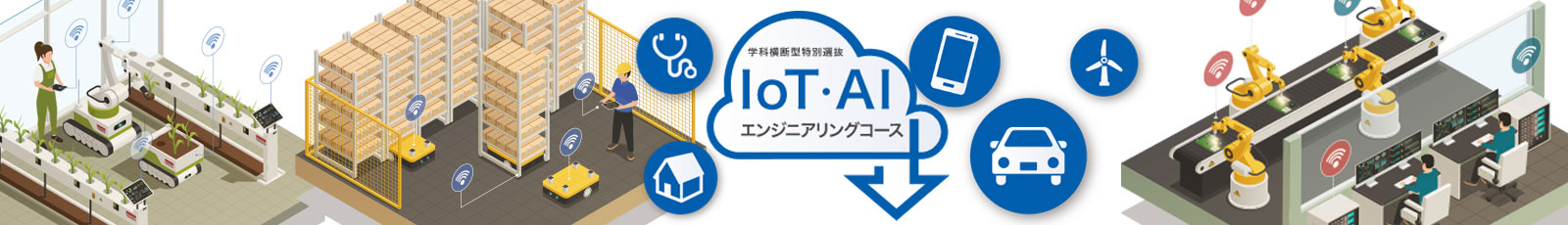A.
昔から様々な機器にコンピュータは入っていますが、現在IoTと呼ばれているコンピュータは、もっと本格的なものです。また、IoT機器の場合、従来のように単にプログラムが組めれば作れるわけではなく、装置を動かす電子回路の知識、機械部品を設計する知識、ネットワークで他のコンピュータと通信させる知識など、様々な分野の知識が必要になります。
IoT・AIエンジニアリングコースでは、IoT機器やAIに使用する組込コンピュータのプログラミング、デジタル回路の設計、電子回路の設計、センサやアクチュエータの回路設計、そして3D CADを用いた機械設計や、3Dプリンタによる部品の製作まで、IoT・AI機器を設計するために必要となる全ての知識を学びます。
従来の機械科、情報科といった、専門分野に特化した学科では対応できないため、コース専門科目に加えて「機械システム工学科」、「電子ロボット工学科」、「情報メディア学科」の内容を横断して学べるのが特徴です。